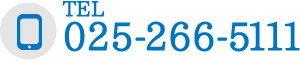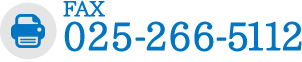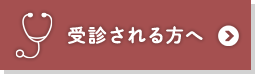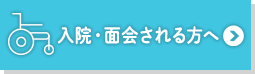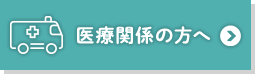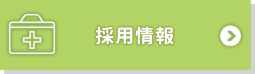頭頸部外科
特徴
頭頸部は、脳より下、鎖骨より上の領域、顔面から頸部全体がここに含まれます。その臓器にできる悪性腫瘍を頭頸部がんといいます。臓器別に、口腔、鼻副鼻腔、咽頭(上、中、下)、喉頭、大唾液腺、甲状腺に分けられています。頭頸部領域の重要な機能として、嚥下、発声、呼吸、さらに感覚器として重要な嗅覚、味覚、聴覚、視覚など生命活動を行う上で重要な機能を担っています。
頭頸部がん治療の特徴は、根治性(癌が治りきること)とQOL(生活の質)の維持が特に重要で、癌が治っても、生活の質が低下すると、今まで可能であったことが出来なくなります。そのため、長期的なQOLを考慮した治療方針を提示しています。具体的には手術、放射線、薬物療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤)を単独あるいは組み合わせて、標準的治療を行いながら、最もその患者さんに適した治療を提供します。
頭頸部外科チームでは、頭頸部外科に加え、放射線治療科、形成外科、口腔外科、言語聴覚士、栄養士、看護師と多職種での合同カンファレンスを行なっており、外科治療、薬物治療、放射線治療のエキスパートが集まり、患者さんの価値観やQOLを重視し、最適な治療を目指しています。
当院独自の試みとして、県内で唯一人工シャント発声(プロボックスR)を個々の患者さんと相談し、実施しております。2023年10月からは頭頸部アルミノックス治療を開始しました。手術不能な再発転移を有する頭頸部がんの患者さんに、有効な治療の選択肢が提示可能となりました。甲状腺疾患においても内視鏡補助下頸部手術(VANS法)を導入しており、こちらも県内唯一の治療施設となっております。頸部に傷跡を残さず美容上優れ、患者さんに非常に喜んでもられる手術と思います。
当科は、新潟県頭頸部悪性腫瘍登録委員会の事務局であり、新潟県内の耳鼻咽喉科医による新規悪性腫瘍登録を1986年より継続しています。それにより新潟県独自の視点から当県患者さんの特徴を見出し、患者さんへの情報還元を目指しています。
研修施設認定
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医研修施設
- 日本頭頸部外科学会認定頭頸部がん専門医認定施設
- 日本内分泌外科学会専門医認定施設
診療対象疾患
1.頭頸部がん(咽頭癌、喉頭癌、口腔癌、鼻副鼻腔癌、唾液腺癌、聴器癌、原発不明癌)
- 再建を用いる拡大手術
- 機能温存を目的とした内視鏡下経口手術
- 化学放射線治療:全身化学療法併用放射線治療や上顎癌に対する選択的動注含む
- 手術不能再発転移症例に対する化学療法(分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬含む)
- 頭頸部アルミノックス治療
2.甲状腺がん(乳頭癌、濾胞癌、髄様癌、未分化癌)、甲状腺腫瘍
- 進行がんに対する気管・食道・喉頭の合併切除・再建手術
- 内視鏡補助下頸部手術(VANS法)は、新潟県内で唯一施術可能施設
- 放射線治療科と放射線ヨウ素内用治療
- 甲状腺内科と新規分子標的薬治療
診療日
| 手術日 | 毎週水曜日、金曜日 | |
|---|---|---|
| 外来日 | 新患 | 午前月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 |
| 再診 | 月曜日~金曜日 | |
外来診療
病棟
西3病棟
スタッフ