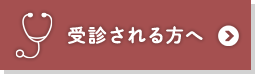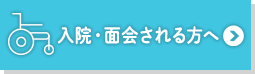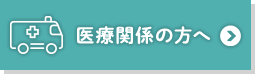- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- がんおよび各種疾患についての説明>
- 泌尿器がん: 腎盂・尿管がん
泌尿器がん: 腎盂・尿管がん
腎盂・尿管がんとは
腎臓でつくられた尿は、腎杯から腎盂、尿管から膀胱へ流れ貯留されます。排尿時には、膀胱から尿道を通って排尿されます。このうち、腎盂と尿管を上部尿路と呼びます。腎盂、尿管と膀胱、尿道の一部は移行上皮と呼ばれる粘膜で構成されています。尿路に発生するがんは、主に移行上皮がんと呼ばれる種類のがんです。腎盂・尿管がんも多くは移行上皮がんです。
腎盂・尿管癌は、泌尿器科癌の中でもまれで、その発生頻度は人口10万人あたり、男性0.1人、女性0.1人程度です。
当院では最近10年間は1年間に20-40人程度の新患の腎盂尿管癌症例を治療しています。
移行上皮がんの発生にはいくつかの危険因子があることがわかっています。中でも化学発がん物質による職業性発生は有名です。具体的には、現在製造使用が禁止されている染色、塗装などで使用されたベンジンやβナフチルアシンなどに長期さらされた場合、また、鎮痛薬であるフェナセチンを長期服用した場合やある種の抗がん剤(シクロフォスファミド)を使用した場合にも発生しやすいといわれています。喫煙も、移行上皮がんの発生の危険率を高くすることが指摘されています。
腎盂・尿管癌は、膀胱癌と同様、尿路内のいろいろな場所に多発、再発しやすい特徴を持っています。腎盂と尿管や、腎盂と膀胱にがんが同時に認められることもあります。腎盂・尿管癌を治療後、20~40%程度、膀胱内に癌が発生することが知られています。逆に膀胱癌の治療後に腎盂尿管癌が発生することはまれです。また腎盂・尿管癌が両側に発生することもまれです。
症状
最も多い症状は、肉眼的血尿です。尿管が血液で詰まった場合や、癌が周囲に進行した場合などには、腰の痛み、背中の痛みがおこることがあります。これらの痛みは、尿管結石によるものと同じような痛みです。腎盂・尿管癌では、尿管が徐々に閉塞した場合には、水腎症と呼ばれる上部尿路の拡張がおこることがあります。この状態があまりに長期にわたると、腎臓の機能がなくなってしまっていることがあります(無機能腎)。
診断
肉眼的血尿が認められた場合、まず出血源を見つけるために膀胱鏡検査が行われます。頻度的には、腎盂・尿管癌より膀胱癌の発生頻度が高いので、まず膀胱癌の存在を疑って検査します。膀胱内に腫瘍が見つからない場合、左右の尿管口より出血がないか確認します。
また、尿の癌細胞の有無を確認する尿細胞診検査を行います。尿細胞診では癌細胞の存在のみならず、癌細胞の異型度も判定できることがあります。
続いてCT検査が行われます。進行度・リンパ節転移の有無・遠隔転移の検索がなされます。
また確定診断を兼ねて逆行性腎盂造影(RP)が実施されることもあります。この検査は、膀胱鏡下に尿管口より細いカテーテルを尿管から腎盂に向けて挿入します。この時、尿管から直接尿を採取し、尿細胞診検査を行い、さらに造影剤を注入します。この検査は異常を明確にすることができる非常に診断的価値の高い検査法です。
がんの拡がりを調べるため、骨シンチグラフィー、胸部X線撮影などを行います。これらの検査で骨、肺、リンパ節、肝臓などへの転移の有無が確認されます。
治療方針
腎盂・尿管癌に対する治療方針は、外科療法が主体です。手術は尿管下端部を残すと、残した尿管にがんが発生しやすいので、がんが発生した片側の腎臓、尿管、さらには膀胱壁の一部も含めた腎尿管全摘、膀胱部分切除(腎尿管全摘術)を施行するのが一般的です。腎臓と腎盂は密接に接触しているため、腎臓全体を摘出することが必要です。同時に膀胱癌を認めるときは内視鏡手術にて治療しますが、治療困難な膀胱癌の合併などがある場合は膀胱全摘除および尿路変向術も必要となることがあります
尿管の癌では、ときに腎臓を摘出せず、尿管の部分切除が行われることもあります。1つしかない腎臓の腎盂や尿管に癌が発生した場合、両側に癌が発生した場合、あるいは悪性度の低い表在性単発腫瘍の場合などでは内視鏡的手術や尿管部分切除などによる腎保存手術が試みられることがあります。
術前の画像診断などより浸潤がんであることが疑われた場合、抗がん剤による化学療法を施行した後、手術を行うこともあります。また、初回治療として化学療法を行い、その効果をみて手術療法や放射線療法を追加することもあります。また、放射線療法もありますが、放射線治療だけでは根治は望めません。年齢や合併症などにより局所治療としての根治手術が難しい方では放射線治療をお勧めすることもあります。また根治手術の結果、術後の再発の危険性が高いと思われる方(壁外浸潤やリンパ節転移が確認された方)には再発率を下げるために抗がん剤の予防投与や放射線治療をお勧めすることがあります。
他の臓器に転移している場合、手術のみで治すことはできません。放射線、抗癌剤を組み合わせた集学的治療が必要です。
現段階での当院の治療方針 (2012,2)
基本の治療方針はまず腎尿管全摘術です。これに術前に抗癌剤、術後に抗癌剤または放射線治療を併用することがあります。術前にリンパ節転移を画像診断にて認めた時は術前抗がん剤治療がお勧めです。
摘出標本の病理診断にて転移を認めるときは、手術、放射線、抗癌剤を組み合わせた集学的治療が必要と思われます。
治療成績・予後
一般的に、腎盂・尿管癌の予後は不良といわれていますが、表在性癌であった場合の予後は良好で5年生存率は85~100%程度です。但し、術後に膀胱内再発がかなり多い(約30-35%)ので定期検診は必要になります。膀胱内再発の多くは内視鏡手術で治療可能です。手術後5年間は必ず外来通院して頂きます。
浸潤癌であった場合は、予後は不良です。尿管壁は非常に薄いため、浸潤性の尿管癌は容易に壁外に進展します。また、浸潤性の腎盂癌では血管やリンパ管の豊富な腎実質内へ進展し、転移することが多いからです。浸潤が強い場合は術後化学療法を加えた方が生命予後を改善する可能性があります。
当院での腎尿管摘出術を受けた方の疾患特異的5年生存率(5年後に腎盂尿管癌で死亡しない確率)は、腎盂癌では病期I(n=41)が100%、病期II(n=10)が100%、病期III(n=75)が73%、病期IV(n=83)が16%です。尿管癌では病期I(n=24)が92%、病期II(n=33)が70%、病期III(n=34)が70%、病期IV(n=26)が33%です。病状が進んだ病期II、IIIでも70%以上の生存率を認めています。リンパ節転移や遠隔転移を認めた方では、いろいろな治療を組み合わせた(抗癌剤治療・放射線治療)集学的な治療が必要と思われます。
退院後の通院について
退院後は膀胱内再発・全身転移の可能性があり、定期的な検診が必要になります。膀胱内の再発は約30-35%に認められます。膀胱内再発の多くは内視鏡手術で治療可能ですので早期発見が大切です。全身転移(遠隔転移・局所再発)の可能性も20~30%に認めます。局所での再発、肺、骨、肝などに転移を見られます。膀胱再発、全身転移などの再発は多くの方では3年以内に認められます。5年を過ぎると再発の頻度は少なくなってきます。
当院では術後5年間の通院(数ヶ月に1回)が必要で、膀胱鏡、尿細胞診、胸部レントゲン写真、CT検査などによる定期的チェックがと考えます。
治療の副作用について
1)外科療法
一方の腎臓を摘出したことによる生活上の制限はあまりなく、副作用もほとんどありません。片方の腎臓を摘出したことにより、人工透析が必要となることは非常にまれです。
手術は全身麻酔で約3時間位かかり、約2−3週間の入院が必要です。浸潤性の腎盂尿管癌では周囲臓器や、下大静脈の合併手術が必要なときは5−6時間も必要とする大手術になります。手術の早期合併症として、出血による輸血の可能性、リンパ節郭清(かくせい:リンパ節を切除すること)後のリンパ液の貯留と炎症および足のむくみ、縫合不全(ほうごうふぜん)、腸閉塞、周囲臓器(直腸、結腸、小腸)損傷などがあります。
出血に対しては輸血が必要になるときがありますが、輸血にはウイルス感染や免疫反応などの危険性が多少あります。それを避ける方法として、あらかじめ自分の血液を採血・貯蔵しておき、手術の際に体に戻す自己血貯血法という方法を採用しています。
手術中・直後の全身に起きる大きな稀な合併症として、心筋梗塞・肺梗塞・脳梗塞・脳出血が0.1%程度発生するといわれています。致命的な合併症で一度起きてしまうと危険な状況に陥る可能性もあります。
2)化学療法(抗癌剤治療)
現段階ではシスプラチンとジェムザールの組み合わせが多く用いられていますが、使用する抗がん剤の種類によって異なり、また個人差もありますが、治療中の主な副作用は骨髄毒性(貧血、白血球減少による感染、血小板低下による出血傾向)、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、手足のしびれ、肝機能障害、腎障害、脱毛、疲労感など、その他予期せぬ副作用もみられることもあります。原則として、これらは抗がん剤投与後2~3週間で改善するため対症療法を行います。強い白血球減少に対しては感染を防ぐために白血球増殖因子(血液を産生する骨髄に作用し、白血球を短期間で多くつくらせる薬)を投与します。
3)放射線療法
放射線の有害事象には放射線治療中に生じてくるもの(早期有害事象)と治療終了後数ヶ月以上経過してから生じてくるもの(晩期有害事象)とがあります。残念ながらこれらの障害の出方や強さをあらかじめ予測する方法はいまのところありません。
早期有害事象は全身的なものと局所的なものがあります。
全身的なものとしては、倦怠感、食欲不振、吐気、血液の変化(白血球、血小板減少など)などがあげられます。
局所的な早期有害事象は半数以上の方に生じますが、その症状の出方や強さはかなり個人差があります。局所の早期有害事象は放射線による粘膜炎の症状として出てきます。症状がでてくるのは治療開始後2~3週目くらいが一般的です。 症状が強い時には、薬剤を使って症状を緩和させます。それでも症状が緩和せず、強くなる場合には、放射線治療を一時休むことになりますが放射線治療を休止するまでに強い症状の出る方は1~2%くらいです。この早期有害事象は一般的には、治療が終了してから2~4週くらいで徐々に治まってきます。
晩期有害事象は放射線治療終了後数ヶ月以降に生じる副作用です。放射線をかけた場所に生じてきます。毛細血管が放射線をかけたために詰まって、血流が悪くなるのが原因の大部分をしめていると考えられています。軽症なら経過観察のみ、または対症療法で様子をみていきますが、重症になると輸血や手術が必要になることもあります。放射線による晩期有害事象は改善するまでに時間がかかるのが特徴で、半年から数年かかることもあります。
放射線治療を受けることで発癌性について心配される方がいらっしゃると思います。放射線治療で誘発される癌の発生時期は、白血病では5年以内に発症することも報告されていますが、固形腫瘍では10年以上後から出てくるとされています。