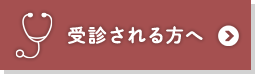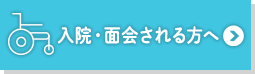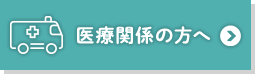- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- がんおよび各種疾患についての説明>
- 泌尿器がん: 腎細胞がん
泌尿器がん: 腎細胞がん
腎細胞がんとは
腎臓は、ちょうど肋骨の下端の高さで、左右、両方にソラマメのようなかたちをした臓器で、血液をこして尿を生成しています。腎臓の実質に発生する腫瘍には、成人に発生する腎細胞がんと小児に発生するウィルムス腫瘍があります。腎臓には良性の腫瘍が発生することもあります。一番頻度が高いのは、腎血管筋脂肪腫です。通常、放置して構わないのですが、5cm以上の大きさになると自然破裂の可能性があり、治療の対象となります。ここでは、成人に発生する腎細胞癌の解説をします。
腎細胞癌の発生頻度は、人口10万人あたり2.5人程度です。男女比は2~3:1で男性に多い傾向があります。当院では1年間に50-70人の新患の腎細胞癌症例を治療しています。
症状
このがんは、大きくなるとさまざまな症状がみられますが、腫瘍の最大径が5cm以下で、何らかの症状があることはまれです。近年、超音波検査やCTなどの普及により、小さな腎がんが見つかるようになり、症状のない場合が増加しています。サイズの大きい腫瘍では、血尿、腹部腫瘤、疼痛などがみられます。また、全身的症状として発熱、体重減少、貧血などをきたすことがあります。まれに、腎細胞癌が産生する物質によって、赤血球増多症や高血圧、高カルシウム血症などが引きおこされることがあります。このがんは、もともと静脈内に進展しやすいのですが、静脈内への腫瘍の進展によって、下大静脈という腹部で一番大きな静脈が閉塞すると、血液が他の静脈を通って心臓に戻るため、腹部体表の静脈が目立ったり、陰嚢内の静脈が目立つ(精巣静脈瘤)現象がおこることがあります。腎細胞癌で発熱や体重減少など全身的な症状を伴っている場合、進行がはやいといわれています。検診などで症状のない腎細胞癌が発見される機会が増えているのですが、腎細胞癌の約2割は、肺や骨に転移した腫瘍がまず発見され、いろいろ調べているうちに腎臓に原発のがんが見つかり、腎がんの肺や骨転移と診断されることがあります。肺に転移が存在しても自覚症状はあまりありません。
診断
超音波検査は簡便で、スクリーニング検査としては非常に診断学的価値のある検査です。腎嚢胞(腎臓に水のたまる袋ができるもの)や良性疾患である腎血管筋脂肪腫などの鑑別にも有用です。さらにCT検査が施行されます。この検査によって、腎の腫瘍性病変の鑑別診断が可能です。また、静脈内の腫瘍塞栓の有無やリンパ節転移の有無などが診断できます。胸部X線写真や肺CTにより肺転移の有無を検索します。また、骨転移の有無を確認するため、骨シンチグラフィが施行されます。
また腎細胞癌には有効な腫瘍マーカーは現段階ではありません。
病期(ステージ)(病気の進み方)分類
T1:最大径が7cm以下で、腎に限局する腫瘍
T1a 最大径が4cm以下で、腎に限局する腫瘍
T1b 最大径が4cmを超えるが7cm以下で、腎に限局する腫瘍
T2:最大径が7cmを超え、腎に限局する腫瘍
T3:腫瘍は主静脈内に進展、または副腎または腎周囲に浸潤するがゲロタ筋膜を越えない
T4:腫瘍はゲロタ筋膜を越えて浸潤し、隣接臓器に浸潤する
N(+), M(+):リンパ節・遠隔転移を認める
治療について
腎細胞癌の治療の主体は外科療法です。病期にかかわらず、摘出できる場合は腎臓の摘出、あるいは腎臓を部分的に摘出することが最も一般的です。肺や骨に転移があっても、腎臓の外科的摘出を考慮します。これは1)腎臓を摘出する手術がそれほど身体にダメージがないこと、2)腎臓を摘出した後、転移巣に対して免疫療法、外科療法などを行うことにより、がんの進行が抑えられることがあること、3)がんをそのままにしていた場合、将来、出血や腹痛、発熱、貧血などが発生し、生活の質が低下することなどを配慮して摘出が行われています。 腎臓は腎の上部に位置する副腎とともにゲロタ筋膜におおわれています。したがって、腎細胞癌に対する外科療法としては、副腎も含めてゲロタ筋膜ごと腎臓を摘出する方法(根治的腎摘手術)が一般的ですが、近年ではゲロタ筋膜に含まれる副腎を同時に摘出するのは、大きな腎細胞癌や副腎の近くに腫瘍があるときだけです。また近年、各種画像診断の普及から、腫瘍サイズが小さい腎細胞癌が発見される機会が増加しています。このような小さい腎細胞癌(3 - 4cm以下)に対しては腎臓を全部摘出せず、腫瘍とともに腎臓の一部のみを摘出(腎部分切除)する手術が行われています。このような手術を受けた場合でも腎臓を全部摘出した場合でも再発率、生存率については大差がないといわれています。根治的腎摘出術では多くの場合では同時にリンパ節郭清術を施行しています。
外科療法以外の方法としては、腎動脈を人工的に閉塞させ、がんに血液が流れ込まないようにする方法(動脈塞栓術)があります。この方法は摘出が不可能な場合や、大きな腫瘍を摘出する場合、手術に先立ち施行されることもあります。
転移巣に対しては、自己の免疫力を高める治療(免疫療法)や分子標的治療を行うことが一般的ですが、転移巣が少数で、腫瘍の大きさや数が変わらない場合、経過観察後あるいは免疫療法後に手術による転移部位の摘出が行われることがあります。肺の転移巣に対する外科療法では長期生存も期待されます。さらに骨、脳転移などに対しても外科療法や放射線療法が行われることがあります。
腫瘍が多発したりしている場合は、免疫療法・分子標的治療が主体となります。腎癌は免疫療法により効果が認められることなどにより、近年、各種の先端医療が試みられています。当院では兄弟姉妹の白血球を利用したミニ移植療法、さらに一部の施設では個々の患者さんの腎がん組織よりワクチンを作成し、これを体内に戻す治療(遺伝子治療)や免疫反応に重要な役割をはたす樹状細胞を用いた治療法が実施されていますが効果については一定の見解は出ていません。
また最近では肺癌の治療などに適応されている分子標的治療が2008年から保険適応になりました。分子標的治療とは体内の特定の分子を狙い撃ちしてその機能を抑えることにより病気を治療する治療法です。正常な体と病気の体の違いあるいは癌細胞と正常細胞の違いをゲノムレベル・分子レベルで解明し、癌の増殖や転移に必要な分子を特異的に抑えたり関節リウマチなどの炎症性疾患で炎症に関わる分子を特異的に抑えたりすることで治療です。腎細胞癌の遠隔転移に対しては、欧米の治療ガイドラインでは第1選択の薬剤と定義されています。本邦でもネクサバール、スーテント、アフィニトール、トーリセルの4つの薬剤が使用可能ですが、長期の治療成績・副作用に関しては不明瞭の部分があります。
また多くの癌においては、抗癌剤治療が通常行われますが、腎細胞癌では有用性は認めらてれていません。腎細胞癌の中で特殊なタイプの組織型の時には抗癌剤の使用が考慮されるときも希にあります。
現段階での当院の治療方針(2012.2)
- 3 - 4cm以下の腫瘍——腎部分切除
- 4cm以上の腫瘍——根治的腎摘出術+リンパ節郭清術
- 術後の補助療法の有用性は報告されていません
- 遠隔転移がある場合
- 可能なら根治的腎摘出術を行います。
肺転移にはインターフェロン(免疫療法)の投与、肺以外にも転移がある時には分子標的治療が行われます。遠隔転移巣が切除可能な時には適応になります。このように、いろいろの治療を組み合わせた集学的な治療が必要になります。
- 可能なら根治的腎摘出術を行います。
副作用・合併症について
手術について
腎臓のみを摘出する手術では合併症は比較的少ないです。全身麻酔で2-3時間の手術です。しかし大きな腎細胞癌では周囲臓器(小腸、大腸など)を合併切除するときもまれにあります。また腎静脈・下大静脈まで腫瘍が進展したときには下大静脈の切開・切除が必要となり、大出血も予想され負担の大きな手術になります。腎臓の機能については、腎臓は左右に2つあり、ひとつの腎臓を摘出することで人工透析が必要となるような腎機能不全に陥ることはまずありません。手術の早期合併症として、出血による輸血の可能性、リンパ節郭清後のリンパ液の貯留と炎症および足のむくみ、縫合不全、腸閉塞、周囲臓器(結腸、小腸、十二指腸)損傷などがあります。
出血に対しては輸血が必要になるときがありますが、輸血にはウイルス感染や免疫反応などの危険性が多少あります。それを避ける方法として、あらかじめ自分の血液を採血・貯蔵しておき、手術の際に体に戻す自己血貯血法を採用しています。
腎部分切除術は2時間前後の手術ですが、腫瘍の位置、腎動静脈との関係、出血などの原因で、手術中の判断にて部分切除から腎摘出手術に変更されることもあります。
手術中・直後の全身に起きる大きな稀な合併症として、心筋梗塞・肺梗塞・脳梗塞・脳出血が0.1%程度発生するといわれています。致命的な合併症で一度起きてしまうと危険な状況に陥る可能性もあります。
動脈塞栓術
一時的な発熱、痛み、腸閉塞や全身衰弱などの副作用があります。手技的にはカテーテルを大腿動脈挿入します。副作用として血栓症(肺梗塞、腎全体の梗塞など)、出血の可能性があります。
免疫療法
個人差もありますが、インフルエンザに似た発熱、関節の痛みなどが認められます。
分子標的治療
インターフェロンなどの免疫療法に比較すると、高頻度に強い副作用を認めます。初期の投与では入院が必要になります。
治療成績と予後について
最近、腎がんは非常に小さく早期で発見されるようになり、治療成績は、T1程度のがんでは90%以上治癒しています。4cm以下で部分切除術(平均2.25cm)を施行した115例中2名では肺転移を認め、2例では対側腎に腎細胞癌の発生を認めています。一方4cm以下で根治的腎摘出術を受けた221名(平均腫瘍径は3.13cm)中24例では再発を認めました。腫瘍径が4-7cmの248名では51例(20.1%)に再発を認めています。7cm以上では167例中72名に(43.1%)に再発を認めました。10cm以上の大きな腫瘍・転移のある腫瘍の成績はより劣ります。また、発熱、著明な体重減少などの症状のあるがんの予後は、症状のないがんより明らかに不良です。
腎細胞癌の再発の特徴としては10年を過ぎた再発を認めることがあることです。多くの再発は8年以内ですが、当院では950例の腎細胞癌患者さんのうち17例が10年を過ぎてから再発を認めました。
再発の部位は肺が最も多いのですが、骨、脳、肝などにも転移を認めることがあります。定期的な外来通院が必要になります。
当科での10年疾患特異生存率(10年間に腎細胞癌で死亡しない率)は全症例(950名)で69.7%、初診時転移の無い患者(802名)さんは80.8%です。腫瘍の大きさが4cm以下で部分切除を受けた方(115名)は100%、腎摘出術を受けた方(221名)は92.5%、4-7cm(252名)では82.4%、7cm以上(158名)では60.4%、病期III(リンパ節転移・腎静脈腫瘍血栓を伴うとき)では44.2%です。治療開始時に遠隔転移のある患者さんで、腎臓の摘出術を受けた方(97名)の生存率は3年・5年疾患特異的生存率は34.8%・25.3%、腎臓の摘出術さらに遠隔転移部の手術を受けた方(22名)の3年・5年疾患特異的生存率は53.3%・37.3%です。